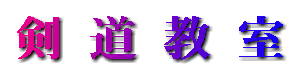
|
| ひとつの動作を行った後、直ちに次の動作が行えるように準備する心で、油断のない態勢を とることである。 相手を打ったときは心残りなく十分に打ち、一度打ったならば必ずこころを残し打ちが弱ければさらに強く打ち、あるいは寸部の油断のないように身構える。 常にいつ何時でも相手の攻撃に応じられる用意をしていなくてはならない。 有効打突の条件は、充実した姿勢、適正な姿勢をもって、竹刀の打突部で打突部位を 刃筋正しく打突し、残心あるものとするとある。従って、残心のない打突は、たとえ確実に 打突していても有効打突としての一本にはならないことを念頭に置いておくことが大切である。 |
| 不動心とは、いかなる場合に遭遇しても、心を動かすことなく、泰然としていることをいう。 心を動かさないということで平常心と同じ意味にとらわれるかも知れないが平常心とは違う ことを知っておこう。 平常心とは思ってもいなかった危機や変事に遭遇しても、それにとらわれないで常日頃持っ ている心と変わらない状態を保ち、的確に対応処置することを言う。 不動心は、思ってもいなかった危機や変事に遭遇しても、さらに強固な意志、頑強な精神に よって、自分の信念、意思をつらぬくことを意味する。 さらに不動心とは、精神の心痛により正常な判断ができなくなったり本心が失われた時、又 生死の境をさまよい意識がもうろうとなった時など、毅然としてこれらの邪念を取り除き、本来 の精神力を正常に戻し、その精神力を正常に働かせ、確固たる信念を貫き危機や変事に 屈せずに立ち向かうことを言う。 剣道の修練にはこの不動心を養うことが重要なことは言うまでもない。 |
| 相手に対して勝ちを得ようとしても、よほど技量の異なったものでなければ、簡単に勝ちを納 めることはできない。自分が勝とうと思うと同時に相手も同じことを思っているからである。 だから、攻めたり、技を駆使して相手の心を乱し、隙を生じさせその隙を逃さず打突し勝ちを手にすることができるのである。 打突する機会は、攻防の中では余りに多く、これをすべて説明することは困難であるが常に 起こりやすい機会は次のようになる。 ①出頭 相手が自分を攻めに出るところ、または技を出そうとする起こりを察知しすかさず打突 する。 ②相手がひくところ 攻め負けて、備えなしに後退したり横に移動するところ。 ③居付いたところ 攻められて心の動きが停滞し動作を起こすことができないところ。 ④技の尽きたところ 打突しても有効打突にならない場合、次の技を繰り出し有効打突を得ることが大切である が、いつかは尽きてしまう。その技の尽きたところや、技から次の技へ移ろうとする切れ目 のところ。 ⑤受け止めたところ 相手の打突を受け止めたとき、受け止められた相手はその瞬間心が居着いて隙が生じ てしまうその隙の生じたところ。 受け止めた方は、受け止めっぱなしでなく、受け止めた瞬間に応じ技を出すことが大切 である。 ⑥心乱れたところ 心に四戒が生じたり、かっこ良くやりたいとか、どうやって打突しょう、どうやって守ろう など、無心でなくなり心が邪念によって乱れたところ。 ⑦実を失って虚となったところ 何かの動揺によって、充実した気力が抜けて、腹に力が無く、心身が自由に動かすことが できなくなったところ。 打突の機会の中に 「三つの許さぬところ」という教えがあるがこれは上記の中の ①出頭 ④技の尽きたところ ③居付いたところ この三つは重要な打突すべき機会とされている。 以上の打突の機会は目で見てわかるものではなく、相手は隙を見せて誘っていることも考え
懸中待、待中懸と言って、懸る中に防ぐ技が含まれ、また待つ中に懸る気持ちや体勢が含まれていることを表す。 剣道は常に心や技の攻防であるため、打突していく動作の中に相手の打突を防ぐ心や体勢が必要である。 又、相手の打突を防いだら、その体勢がすぐ攻撃に転じられることが大切です。 文章や言葉では簡単に説明できるが、実際にこの境地になるのは大変な苦労が必要であり、 「懸待一致」とは、動作としては攻撃しているが、心の中では油断するなということである。 |